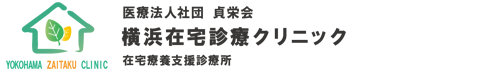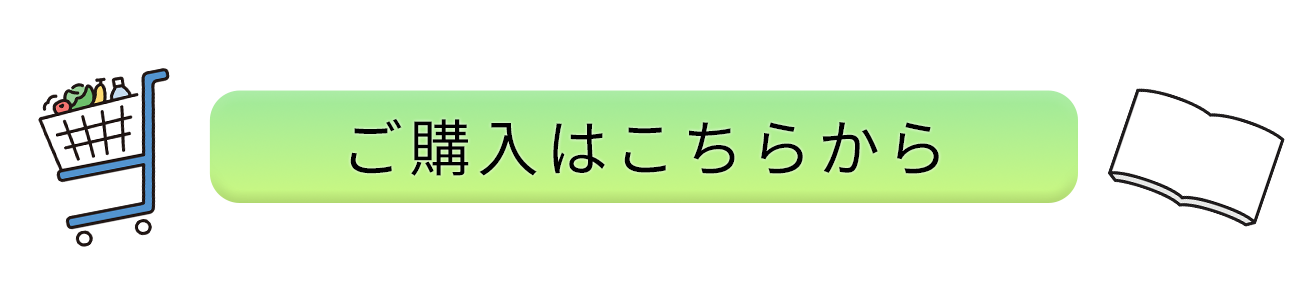患者さんの生活の中に入っていくのが在宅医療
在宅医療は、病院の医療とは異なっています。最も大きな違いは診療を行う場所、環境です。
病院では、診察室にいる医師のところへ患者さんに来てもらうことになります。一方、在宅医療では病院とは逆に、患者さんの生活のなかにわれわれ医療スタッフが入っていきます。
環境が変われば、それに応じて自ずと医療も変わってきます。例えば高血圧の治療では、病院ならば医師の判断材料になるものは検査などの数値と、患者さんや付き添いの家族の話が中心になります。その結果、血圧や検査値を見て、数値がよくなっていれば治療を継続してもらい、悪くなっていれば薬を変えたり増やしたりする、そういう対症療法がどうしても多くなります。
しかし在宅医療は、医師が患者さんの家のなかに行くのですから、家を見ることが大切だと考えられています。普段口にしている食事や飲料、服薬している薬、生活や睡眠の環境、家族との関わりといった、診察室ではわからないたくさんの判断材料を得ることができるからです。
患者さんの血圧が前より上がっていた場合、それは知らないうちに塩分の多い食品をたくさん食べていたのかもしれませんし、家族の心配事があって眠れず、ストレスがかかっていたのかもしれません。
そうした生活のなかの原因や注意したいポイントを確認しながら、具体的な対処法を一緒に考えていくことができます。
病院では、診察室にいる医師のところへ患者さんに来てもらうことになります。一方、在宅医療では病院とは逆に、患者さんの生活のなかにわれわれ医療スタッフが入っていきます。
環境が変われば、それに応じて自ずと医療も変わってきます。例えば高血圧の治療では、病院ならば医師の判断材料になるものは検査などの数値と、患者さんや付き添いの家族の話が中心になります。その結果、血圧や検査値を見て、数値がよくなっていれば治療を継続してもらい、悪くなっていれば薬を変えたり増やしたりする、そういう対症療法がどうしても多くなります。
しかし在宅医療は、医師が患者さんの家のなかに行くのですから、家を見ることが大切だと考えられています。普段口にしている食事や飲料、服薬している薬、生活や睡眠の環境、家族との関わりといった、診察室ではわからないたくさんの判断材料を得ることができるからです。
患者さんの血圧が前より上がっていた場合、それは知らないうちに塩分の多い食品をたくさん食べていたのかもしれませんし、家族の心配事があって眠れず、ストレスがかかっていたのかもしれません。
そうした生活のなかの原因や注意したいポイントを確認しながら、具体的な対処法を一緒に考えていくことができます。
医師ー患者という縦の関係ではなく、耳を傾け、共感する
しかし在宅医療では、そうした医師ー患者という“縦”の関係ではありません。在宅医療の主役は、あくまで患者さんです。医師も含めて医療・介護のスタッフは。患者さんの横にいて必要なときにサポートをさせていただくのが仕事です。
ですから、当クリニックでは患者さんのお宅に上がるときにも、靴をそろえる、挨拶をするなど、「患者さんの生活に入らせていただく」という姿勢を行動で示せるように意識しています。医師が患者さんと接するときも上から見下ろすのではなく、座って患者さんと同じ目線の高さで会話をすることを心掛けています。
一般の方からすれば、わざわざ説明するまでもない礼儀作法かもしれませんが、病院勤務の長い医師のなかには、患者さんのお宅でも病院の廊下を歩くようにズカズカと上がり、立ったまま話すような人も時折見かけます。そうしたふるまい1つで、患者さんやご家族の在宅医療の印象が変わってしまうこともあるので、そこは注意しなければならないところです。
また、在宅医療でいちばん大事なのは、患者さん・ご家族が安心して生活できるように「不安を取る」ということです。
患者さんやご家族が生活には大きな支障がない症状を訴えてくるとき、「そんなの大丈夫」と軽くあしらう医師もいます。しかし私たちは、そういう小さな不安・不満もすぐに否定せず、耳を傾け、共有するようにしています。在宅医は、気になる症状がどういう原因から来ているかも推測がつきますから、苦痛や不快さを解消したり、和らげたりする方法をアドバイスすることができます。
「話を聞いてもらえた」「気になるところを診てもらえた」というだけで、高齢者は安心されることも多いものです。そうした日々のやり取りの積み重ねが、確かな信頼関係につながっていきます。
ですから、当クリニックでは患者さんのお宅に上がるときにも、靴をそろえる、挨拶をするなど、「患者さんの生活に入らせていただく」という姿勢を行動で示せるように意識しています。医師が患者さんと接するときも上から見下ろすのではなく、座って患者さんと同じ目線の高さで会話をすることを心掛けています。
一般の方からすれば、わざわざ説明するまでもない礼儀作法かもしれませんが、病院勤務の長い医師のなかには、患者さんのお宅でも病院の廊下を歩くようにズカズカと上がり、立ったまま話すような人も時折見かけます。そうしたふるまい1つで、患者さんやご家族の在宅医療の印象が変わってしまうこともあるので、そこは注意しなければならないところです。
また、在宅医療でいちばん大事なのは、患者さん・ご家族が安心して生活できるように「不安を取る」ということです。
患者さんやご家族が生活には大きな支障がない症状を訴えてくるとき、「そんなの大丈夫」と軽くあしらう医師もいます。しかし私たちは、そういう小さな不安・不満もすぐに否定せず、耳を傾け、共有するようにしています。在宅医は、気になる症状がどういう原因から来ているかも推測がつきますから、苦痛や不快さを解消したり、和らげたりする方法をアドバイスすることができます。
「話を聞いてもらえた」「気になるところを診てもらえた」というだけで、高齢者は安心されることも多いものです。そうした日々のやり取りの積み重ねが、確かな信頼関係につながっていきます。