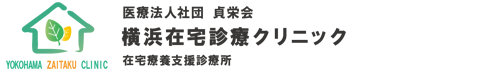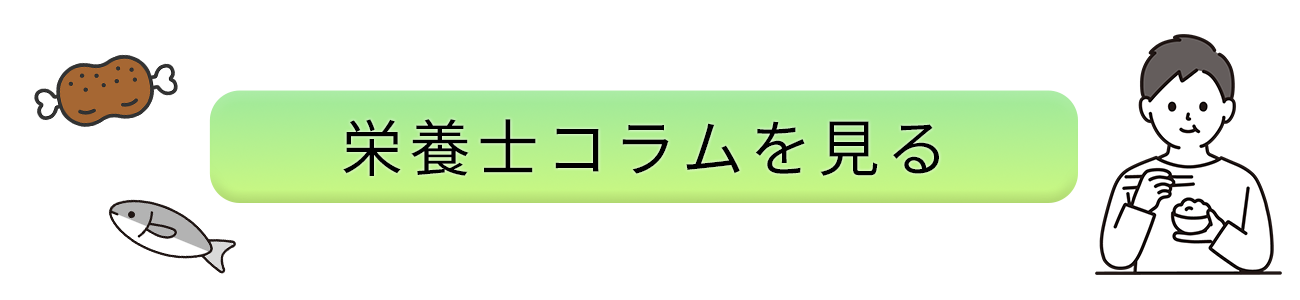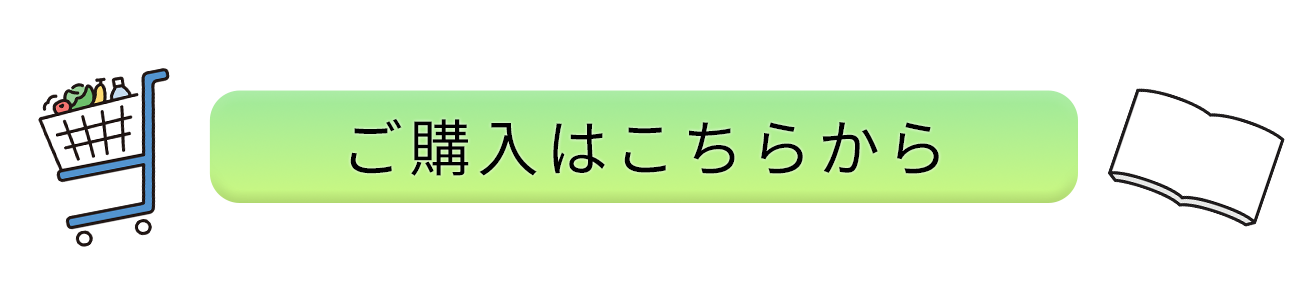病院での医学的な正しさより、患者さんの思いを優先
病院は「病気を治す場所」ですから、何より治療が優先されます。数値が悪いときは、それを良くするために医師が「こうしてください」と治療法を指示し、患者さんが従う形になります。
しかし、在宅医療はそうではありません。
在宅医療チームが入っていくのは「患者さんの生活の場」です。そこで医師が頭ごなしに、「医者の言うことを聞け」という態度で患者さんに接するのは違うと思います。
しかし、在宅医療はそうではありません。
在宅医療チームが入っていくのは「患者さんの生活の場」です。そこで医師が頭ごなしに、「医者の言うことを聞け」という態度で患者さんに接するのは違うと思います。
また患者さんが療養生活のなかで何を大切にしたいかは、人によってそれぞれ違います。子どもや孫たちとの外食が大切という人もいれば、食事は質素でもいいけれどタバコはやめたくないという人もいます。
日常生活の介護でも、ヘルパーや看護師にきめ細かく支援をしてほしい人もいれば、家事支援などは最小限でいいので、1人の時間を大切にしたい人もいます。
それぞれの人の価値観を尊重しながら、その人が自宅で長く生活を続けるために、必要な治療・支援は何なのかという視点で医療・介護の方針を検討していくことが重要です。
日常生活の介護でも、ヘルパーや看護師にきめ細かく支援をしてほしい人もいれば、家事支援などは最小限でいいので、1人の時間を大切にしたい人もいます。
それぞれの人の価値観を尊重しながら、その人が自宅で長く生活を続けるために、必要な治療・支援は何なのかという視点で医療・介護の方針を検討していくことが重要です。
生活を楽しみながら、家で長く過ごせるように
特に高齢期になると、糖尿病や高血圧、肥満といった生活習慣病を抱える人が多くなります。
こうした慢性疾患は、長期間にわたって根気よく食事制限や運動療法などの生活改善を続けていかなければなりません。あまり厳しくしすぎると息が詰まり、結局は続かなくなります。
患者さんの状況に応じて、時々息抜きもしながら、続けられる生活指導を考え提案をしていくのが、在宅医療ならではの支援です。
実際、塩分や糖質・カロリーを控える食事指導でも、その具体的な方法はいろいろと考えられます。
こうした慢性疾患は、長期間にわたって根気よく食事制限や運動療法などの生活改善を続けていかなければなりません。あまり厳しくしすぎると息が詰まり、結局は続かなくなります。
患者さんの状況に応じて、時々息抜きもしながら、続けられる生活指導を考え提案をしていくのが、在宅医療ならではの支援です。
実際、塩分や糖質・カロリーを控える食事指導でも、その具体的な方法はいろいろと考えられます。
例えば、食事のときになんでも醤油をかけてしまう年配の方がいたとします。高血圧があって減塩をしてほしい、というときに「醤油をかけるのをやめて」と言うと、本人は抵抗を感じるはずです。
本人が面倒と感じることや、ただ我慢をするだけの制限は長く続かないものです。それより「使っている醤油を普通の醤油ではなく、減塩タイプにしてみては」と提案すると、本人も「それならできそう」と思ってくれますし、治療の意欲も高まります。
最近の研究では、高齢者ではあまり厳格にヘモグロビンA1cを下げなくても、好きなものをもりもり食べている人の方が長命、というデータもあります。ヘモグロビンA1cは高齢者は年齢の10分の1、つまり70代なら7、80代なら8を目安にするといいとされています。
たまの外食や記念日などにご馳走を食べたのであれば、その後、しばらくは質素な食事を心掛ける、というのでもOKです。
ほかにも、調味料や麺類などの主食を糖質オフのタイプに替える方法もありますし、糖尿病の人のための糖質・カロリーを控えた配食サービスも出てきています。自分では調理が難しい人は、そうした市販品を活用するのもいいと思います。
本人が面倒と感じることや、ただ我慢をするだけの制限は長く続かないものです。それより「使っている醤油を普通の醤油ではなく、減塩タイプにしてみては」と提案すると、本人も「それならできそう」と思ってくれますし、治療の意欲も高まります。
最近の研究では、高齢者ではあまり厳格にヘモグロビンA1cを下げなくても、好きなものをもりもり食べている人の方が長命、というデータもあります。ヘモグロビンA1cは高齢者は年齢の10分の1、つまり70代なら7、80代なら8を目安にするといいとされています。
たまの外食や記念日などにご馳走を食べたのであれば、その後、しばらくは質素な食事を心掛ける、というのでもOKです。
ほかにも、調味料や麺類などの主食を糖質オフのタイプに替える方法もありますし、糖尿病の人のための糖質・カロリーを控えた配食サービスも出てきています。自分では調理が難しい人は、そうした市販品を活用するのもいいと思います。
▼▼▼当法人の管理栄養士が随時レシピ紹介中!こちらもあわせてご覧ください▼▼▼
在宅医療チームは、患者さんがその人らしい楽しみをもちながら、長く治療・療養を続けていけるように支援します。治療方針で疑問や困難を感じたときは、医師とよく相談をしてください。