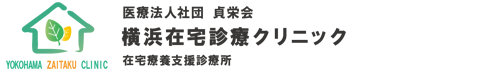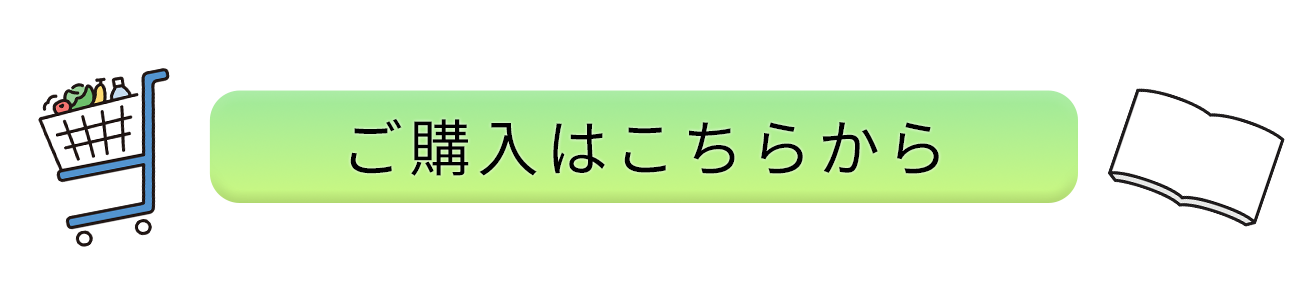家族にも、それぞれ異なる思いがあるもの
最終段階の治療方針を巡って、家族間で意見が割れるというのはよくあることです。家族と言っても、年齢や立場、介護の関わり方などによって考え方は異なります。
よくあるのが、本人の近くで介護をしている人と、離れた場所にいる人との間隔の差です。
近くで介護をしている人は、高齢者の病気の経過や体調がどういう段階にあって、本人がどんな思いでいるかを日ごろから肌で感じています。そのため、本人が「もう治療は十分」というときは、その意向を受け入れやすいと思います。
しかし、遠くにいる人にはその現実が伝わらないことがあります。
高齢の親の元へ、息子・娘が年に数回帰省するといった場合、親はそのときだけは頑張って元気そうに振舞ったりします。その結果、離れて住む子どもの記憶のなかにあるのは、元気だった頃の父親・母親の姿のままです。そこで急に親の命の危機を知らされると動転してしまい、治療してほしいと強く求めることがあります。
よくあるのが、本人の近くで介護をしている人と、離れた場所にいる人との間隔の差です。
近くで介護をしている人は、高齢者の病気の経過や体調がどういう段階にあって、本人がどんな思いでいるかを日ごろから肌で感じています。そのため、本人が「もう治療は十分」というときは、その意向を受け入れやすいと思います。
しかし、遠くにいる人にはその現実が伝わらないことがあります。
高齢の親の元へ、息子・娘が年に数回帰省するといった場合、親はそのときだけは頑張って元気そうに振舞ったりします。その結果、離れて住む子どもの記憶のなかにあるのは、元気だった頃の父親・母親の姿のままです。そこで急に親の命の危機を知らされると動転してしまい、治療してほしいと強く求めることがあります。
当クリニックでもそうした意見の相違は時折あります。このような場合は、息子さん娘さんに親御さんの家へ行ってもらい、現在の本人の姿を見てもらうようにしています。
最終段階が近づいている人は、半年も会わずにいれば、状態が相当に落ちています。現在の本人を実際に見て、話をしてもらえば、本人が望まない治療をいつまでも強いるような人はそれほど多くはありません。
また最終段階の治療方針についての考え方は、世代やその人の環境、ライフステージによっても変わってきます。
私の印象では、親族のなかでも配偶者や本人のきょうだいなどの同年代の人は、年を取る大変さを知っていますから、本人の意向に共感されることが多いです。それに対して息子・娘世代は、インターネットや本でも情報を調べられますから、治療法探しに懸命になられる方もいます。
子ども世代が独身か既婚かによっても、意見は変わってくるのかもしれません。私自身の経験からしても、独身の人と自分の家庭をもっている人では、親の死による喪失感もとらえ方が異なるように思います。
最終段階が近づいている人は、半年も会わずにいれば、状態が相当に落ちています。現在の本人を実際に見て、話をしてもらえば、本人が望まない治療をいつまでも強いるような人はそれほど多くはありません。
また最終段階の治療方針についての考え方は、世代やその人の環境、ライフステージによっても変わってきます。
私の印象では、親族のなかでも配偶者や本人のきょうだいなどの同年代の人は、年を取る大変さを知っていますから、本人の意向に共感されることが多いです。それに対して息子・娘世代は、インターネットや本でも情報を調べられますから、治療法探しに懸命になられる方もいます。
子ども世代が独身か既婚かによっても、意見は変わってくるのかもしれません。私自身の経験からしても、独身の人と自分の家庭をもっている人では、親の死による喪失感もとらえ方が異なるように思います。
最も大事なのは、「本人がどうしたいか」
最終段階の治療方針をめぐり、家族間の意見が対立したとき、いちばん基本の拠り所となるのが、やはり本人の意思です。
本人が意思表示をできるときは「本人がどうしたいか」を確認し、意思表示が難しくなっているときは「本人ならどう考えるだろうか」を想像してみてください。
家族には、家族としての思いがあるのは当然です。「1日でも長く生きてほしい」「別れたくない」と思うものですが、それを少しだけ抑えて「どうしたら本人が、最期の時までその人らしくいられるか」を考え、そこに寄り添ってあげてほしいと思います。
在宅医療チームも加わって何度も話し合いを重ねると、8、9割の人は「このまま家にいたい(本人は家にいたいと思うはず)」という結論になります。あとは本人を中心にして、チームのみんなで決めた方針を実現していけばいいだけです。
本人が意思表示をできるときは「本人がどうしたいか」を確認し、意思表示が難しくなっているときは「本人ならどう考えるだろうか」を想像してみてください。
家族には、家族としての思いがあるのは当然です。「1日でも長く生きてほしい」「別れたくない」と思うものですが、それを少しだけ抑えて「どうしたら本人が、最期の時までその人らしくいられるか」を考え、そこに寄り添ってあげてほしいと思います。
在宅医療チームも加わって何度も話し合いを重ねると、8、9割の人は「このまま家にいたい(本人は家にいたいと思うはず)」という結論になります。あとは本人を中心にして、チームのみんなで決めた方針を実現していけばいいだけです。