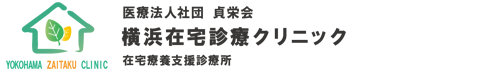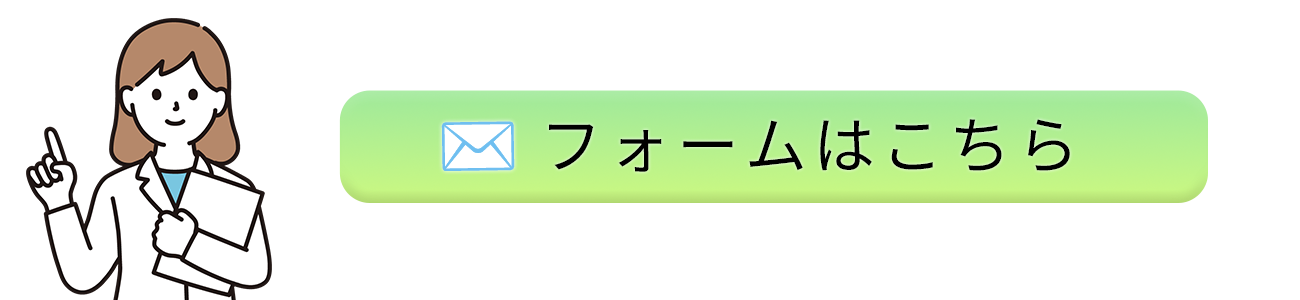家族が「気づける」在宅医療のサインとは?
在宅医療を支えるご家族の「気づき」が、患者さんにとって最良のケアにつながることがあります。
日々の診療の中で感じている「家族だからこそ気づけるサイン」について、在宅医療の今とともにお伝えします。
日々の診療の中で感じている「家族だからこそ気づけるサイン」について、在宅医療の今とともにお伝えします。
在宅医療は「生活を診る」時代へ
かつての在宅医療は、薬の処方や軽い診察などの「延長線上の医療」として受け止められていた時期がありました。
しかし今では、がんの緩和ケアや輸血、心不全末期への対応など、医療の高度化が進み、在宅でも病院に近いレベルのケアが提供されるようになっています。
とはいえ、在宅医療の本質は変わりません。
医師が診るのは「病気」ではなく「生活」そのもの。患者さんの暮らしの中に寄り添い、家族のまなざしと連携する医療が求められているのです。
しかし今では、がんの緩和ケアや輸血、心不全末期への対応など、医療の高度化が進み、在宅でも病院に近いレベルのケアが提供されるようになっています。
とはいえ、在宅医療の本質は変わりません。
医師が診るのは「病気」ではなく「生活」そのもの。患者さんの暮らしの中に寄り添い、家族のまなざしと連携する医療が求められているのです。
家族だからこそ気づける変化
医師や看護師が気づく前に、実はご家族の方が変化を察しているケースは少なくありません。
たとえば…
たとえば…
- 食事の量が急に減った
- 好きだったものを食べなくなった
- 声のトーンが小さくなった/言葉が少なくなった
- ペットボトルのフタを開けるのに苦労している
- トイレの失敗が増えた
- 表情がぼんやりしてきた
こうした“ささいな変化”は、体力や認知機能の低下、さらには終末期への入り口であることも。
変化を共有することが医療につながる
私たち医療者が望むのは、「正しい情報を、正しいタイミングで受け取ること」。
ご家族が「最近ちょっと変だな」と思ったことを、遠慮なく私たちに共有してください。医療的な判断はそこからです。
逆に、共有が遅れてしまうと「もっと早くわかっていれば対応できたかもしれない」と悔やむ場面もあります。
ご家族が「最近ちょっと変だな」と思ったことを、遠慮なく私たちに共有してください。医療的な判断はそこからです。
逆に、共有が遅れてしまうと「もっと早くわかっていれば対応できたかもしれない」と悔やむ場面もあります。
「がんばりすぎない覚悟」で在宅医療を
在宅医療というと、「家で最期まで看取る覚悟が必要」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。
少しずつ「つながる」ことが大切です。
少しずつ「つながる」ことが大切です。
- 最初は通院との併用で始める
- 必要に応じて施設と連携する
など、柔軟な関わり方が可能です。大切なのは、家族だけで抱え込まず、プロの力を借りながら、その人らしい最期に向けてゆっくりと準備していくことです。