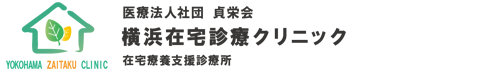「元気なうちに相談?」認知症と在宅医療、始めるタイミングとは
「体は元気だから、まだ大丈夫」「医者にかかるほどではない」そんなふうに考えている方も多いかもしれません。
しかし、認知症という病気は、人によって症状の現れ方も進行のスピードも異なり、“いつから医療や介護を入れるべきか”の判断がとても難しい病気です。
実際、在宅医療の現場では、「もっと早く相談してもらえたら、もっと選択肢があったのに…」と思う場面が少なくありません。
今回は、在宅医療の視点から「認知症の人が医療とどう関わっていくべきか」、そして「相談のタイミング」についてご紹介します。
しかし、認知症という病気は、人によって症状の現れ方も進行のスピードも異なり、“いつから医療や介護を入れるべきか”の判断がとても難しい病気です。
実際、在宅医療の現場では、「もっと早く相談してもらえたら、もっと選択肢があったのに…」と思う場面が少なくありません。
今回は、在宅医療の視点から「認知症の人が医療とどう関わっていくべきか」、そして「相談のタイミング」についてご紹介します。
認知症の在宅医療、実際に多いのはどんなケース?
在宅診療を行っていると、認知症の方を診ることは少なくありません。
ただし、実際に訪問診療が導入されるのは「日常生活に支障をきたすようになった進行したケース」が多い傾向にあります。
たとえば、以下のような状況です。
比較的症状が軽く、自宅で生活が出来ているうちは「まだ医療にはつながらなくて大丈夫」と思われるかもしれません。
しかし、こうした“限界を超えた状態”になってから医療にアクセスしようとしても、すでに選べる手段は限られてしまっているのが現実です。
ただし、実際に訪問診療が導入されるのは「日常生活に支障をきたすようになった進行したケース」が多い傾向にあります。
たとえば、以下のような状況です。
- 夜間に大声を出してしまう
- 家の外を徘徊してしまう
- 排泄がうまくできず、失禁やトイレの詰まりが頻発する
- 服薬管理ができず、薬の過不足が生じている
- 老人ホームに入居し、通院が困難になった
比較的症状が軽く、自宅で生活が出来ているうちは「まだ医療にはつながらなくて大丈夫」と思われるかもしれません。
しかし、こうした“限界を超えた状態”になってから医療にアクセスしようとしても、すでに選べる手段は限られてしまっているのが現実です。
在宅医療を始めるタイミングはいつ?
実は、「この状態になったら在宅医療を始めるべき」といった明確な基準はありません。
大切なのは、「困りごとが起きたときに、すぐ相談できる体制を持っているかどうか」です。
在宅医療を検討するきっかけになりやすいサインには、以下のようなものがあります。
こうしたサインが見られたとき、「もう在宅医療が必要な段階かもしれない」と一度立ち止まってみることが大切です。
大切なのは、「困りごとが起きたときに、すぐ相談できる体制を持っているかどうか」です。
在宅医療を検討するきっかけになりやすいサインには、以下のようなものがあります。
- 排泄トラブルが目立つようになった(トイレが詰まる、隠すなど)
- 家族の顔がわからなくなるなど、人間関係に支障が出はじめた
- 通院や服薬が一人では管理できなくなってきた
- 家族だけでは対応に限界を感じてきた
こうしたサインが見られたとき、「もう在宅医療が必要な段階かもしれない」と一度立ち止まってみることが大切です。
早めに相談しておくことの大きな意味
実際には、多くの方が「もう無理かもしれない」と感じてから初めて相談に来られます。
しかし、その段階では「すぐに施設に入るしかない」といった、限られた選択肢しか残っていないことも少なくありません。
だからこそ、「いざというときに備えて、元気なうちから相談しておく」ことが大切なのです。
相談先としては、かかりつけのケアマネジャー、または訪問診療クリニックの連携室などがあります。
すぐに診療を始めなくても、「このくらいになったら在宅医療をお願いしたい」と伝えておくことで、いざという時にスムーズな連携ができます。
しかし、その段階では「すぐに施設に入るしかない」といった、限られた選択肢しか残っていないことも少なくありません。
だからこそ、「いざというときに備えて、元気なうちから相談しておく」ことが大切なのです。
相談先としては、かかりつけのケアマネジャー、または訪問診療クリニックの連携室などがあります。
すぐに診療を始めなくても、「このくらいになったら在宅医療をお願いしたい」と伝えておくことで、いざという時にスムーズな連携ができます。
医療だけじゃない。生活全体を支える“在宅医”の存在
認知症の相談というと、「薬を出してもらう」「診断をしてもらう」といった医療的な支援を思い浮かべるかもしれません。
でも、在宅医療では、それ以上のサポートが求められることが多いのです。
在宅医は、医療だけでなく生活全体を支える「トータルケアの相談役」としての役割を担います。
ときには「ご家族で話しにくいこと」も、第三者の立場で整理し、代弁することができます。
でも、在宅医療では、それ以上のサポートが求められることが多いのです。
- 今の家の環境で安全に生活できるか
- 介護保険をどう活用するか
- 家族関係はどうか(介護者が疲弊してないか)
- 施設入居を視野に入れる時期はいつか
在宅医は、医療だけでなく生活全体を支える「トータルケアの相談役」としての役割を担います。
ときには「ご家族で話しにくいこと」も、第三者の立場で整理し、代弁することができます。
大切なのは“相談できる関係性”をつくること
認知症の症状や進行は一人ひとり違います。
だからこそ、「こうなったら医療が必要」とは一概に言えません。
でも、「この人に相談してみよう」という関係性を早くから持っておくことで、いざという時に慌てず、本人も家族も納得のいく選択ができます。
「まだ元気だから」は、医療と関わらない理由にはなりません。
元気なうちだからこそ、将来の備えとして“医療とつながる一歩”を考えてみてください。
だからこそ、「こうなったら医療が必要」とは一概に言えません。
でも、「この人に相談してみよう」という関係性を早くから持っておくことで、いざという時に慌てず、本人も家族も納得のいく選択ができます。
「まだ元気だから」は、医療と関わらない理由にはなりません。
元気なうちだからこそ、将来の備えとして“医療とつながる一歩”を考えてみてください。